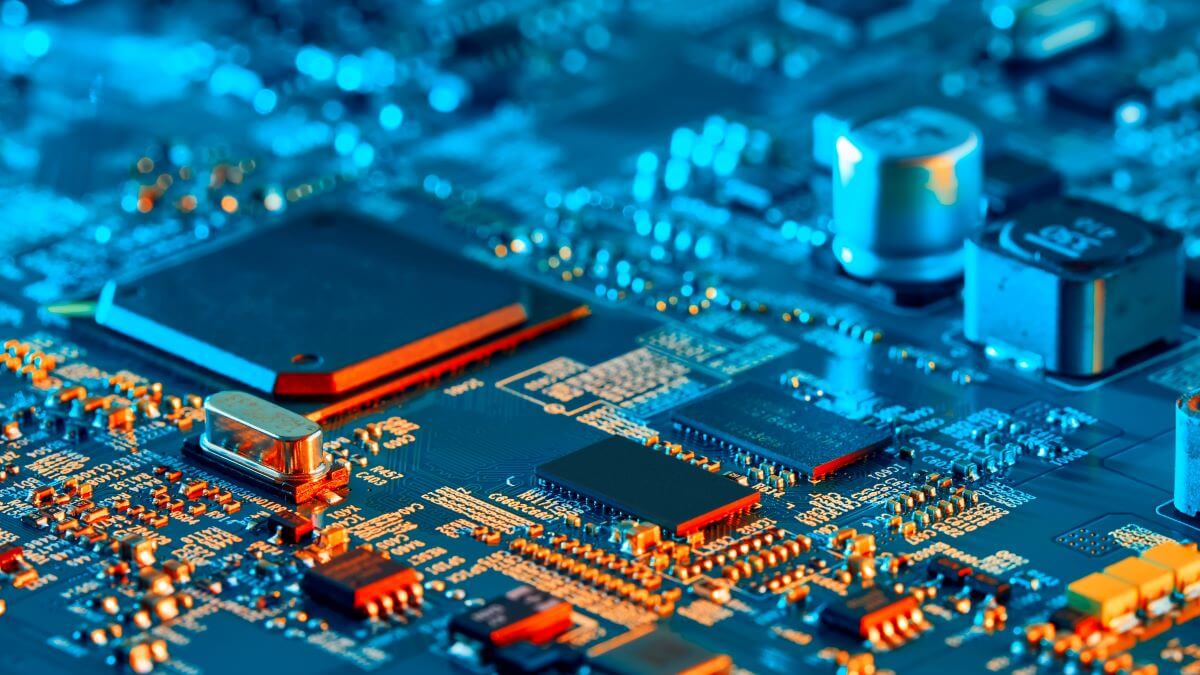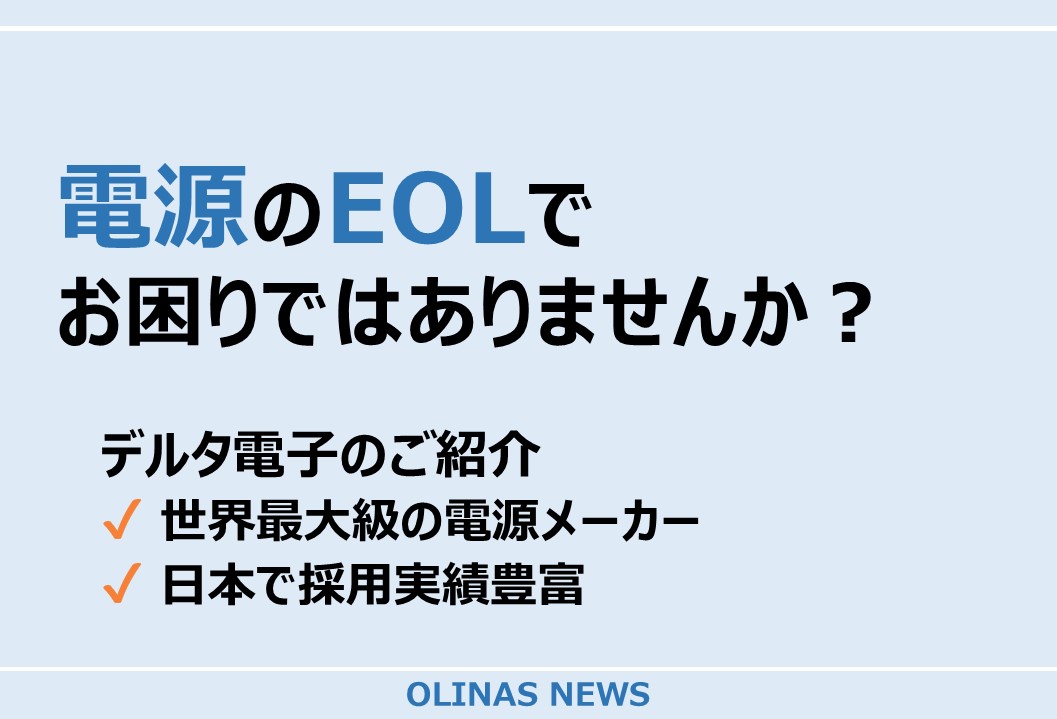オペアンプによるIV変換回路で発生するノイズは、帰還抵抗(IV変換抵抗)で発生する熱雑音、オペアンプの入力電圧ノイズ、および、オペアンプの入力電流ノイズを考慮する必要があります。
1.帰還抵抗(IV変換抵抗)の熱雑音
帰還抵抗で発生する熱雑音(=√4kT×Rf×B)は、そのまま出力に現れます。PDから見た等価負荷抵抗(≒Rf/A)にはなりませんから、誤解のないよう注意してください。
周波数特性はRfとCfで決まる1次ローパス特性(カットオフ周波数fc=1/2πRfCf)となり、入力容量Cinは、PDの端子間容量+オペアンプの入力容量+その他の寄生容量を表していますが、この値の変化は、ほとんど影響しません。シミュレーションで確認してみてください。
IV変換回路の出力ノイズを計算するには、周波数帯域としてB=fc×1.57(1次ローパス特性の場合の等価雑音周波数帯域)を使えばよいのですが、後段の周波数特性が影響する場合には、合成周波数特性での等価周波数帯域で計算する必要があります。
2.オペアンプの入力電圧ノイズ
オペアンプ回路の入力電圧ノイズVnoiseによる出力ノイズは、Vnoise×Gnとなります。ここでGnとはノイズゲインと呼ばれるもので、非反転入力端子から見たゲインです。IV変換回路は、一見すると、ゲイン1のバッファ接続となっていますが、入力容量Cinがあるため、高域の周波数でゲイン>1となります。
まずは、シミュレーションを見てください。この結果を見ると、周波数特性が台形状で、バンドパスフィルタの様な特性になっています。低域の特性は、ゲイン1から平坦部分まで増加しており、ほぼ、カットオフfc=1/2πRfCfのハイパス特性と見てよいでしょう。平坦部分のゲインは、(Cin+Cf)/Cfとなり、かなりのゲインがあります。Cinが大きくなると平坦部分のゲインも増大しますので、出力ノイズの大きさに対してもPDの端子間容量が「悪さ」をしているわけです。高域の減衰は、オペアンプのオープンループ特性による減衰です。
注目しなければならないのは、目的とする信号周波数帯域は、概ね、fc=1/2πRfCfの程度であるにも関わらず、ノイズゲイン特性は、より高域まで伸びていることです。ノイズ特性を最適化するには、後段での帯域制限が必要となります。出力ノイズの計算は、煩雑となるため割愛しますが、私が経験した例では、意外に大きな値になりました。
3.オペアンプの入力電流ノイズ
現実のオペアンプの入力端子は、バイアス電流が流れます。この入力電流にはランダムな揺らぎ、つまり、電流ノイズがあります。この電流は、IV変換回路では、すべて帰還抵抗Rfに流れますので、Inoise×Rfの電圧ノイズが帰還抵抗の両端に発生します。回路内での発生場所が帰還抵抗の熱雑音と同じですから、周波数特性も同一となります。
出力ノイズの計算は、「上記1.」で、熱雑音(=√4kT×Rf×B)の代わりに入力電流ノイズによる電圧ノイズ(Inoise×Rf×√B)とすれば、計算することができます。等価雑音周波数帯域Bについてもまったく同じ扱いとなります。
IV変換回路には、JFET入力タイプ(または、CMOSタイプ)のオペアンプが使われる例が多いのですが、これらは、入力電流が極めて小さく、必然的に、入力電流ノイズも小さいため、通常は、入力電流ノイズは無視できるレベルと考えても大丈夫です。バイポーラタイプのオペアンプを使う場合には、入力電流ノイズによる出力ノイズが支配的になる可能性が大ですので、(特に、帰還抵抗が数KΩ以上の時には)きちんと出力ノイズを計算しておくことをお勧めします。
今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、リニアテクノロジーのサイトよりLTspiceIVをダウンロードしてご利用下さい。