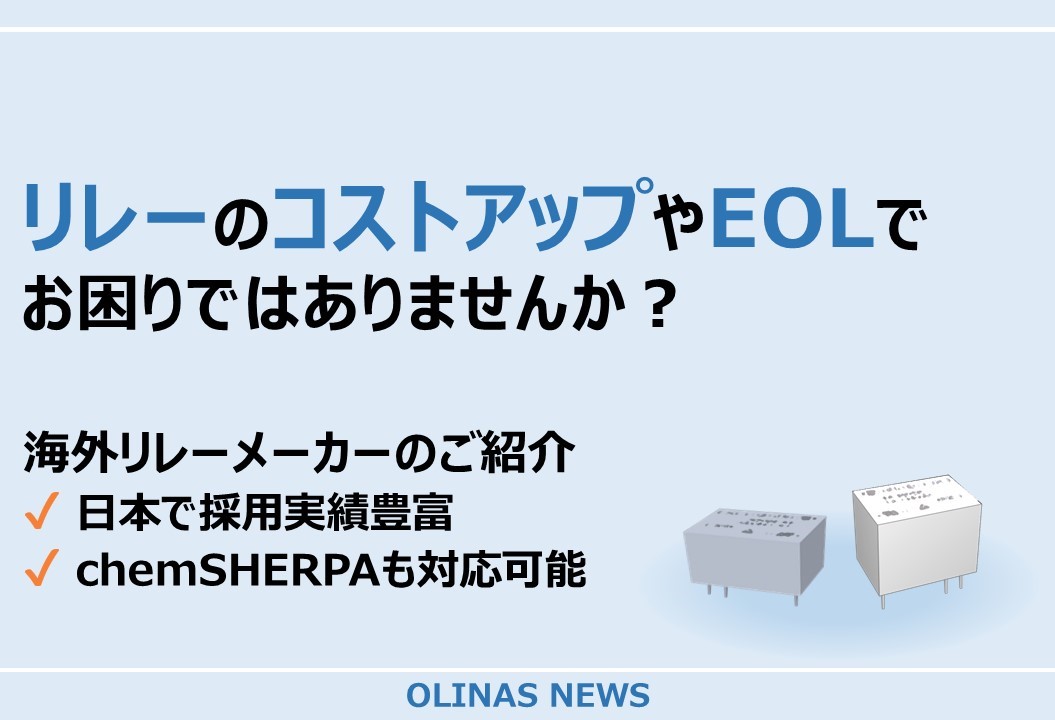RC回路は、これまでに何度か取り上げたこともある、抵抗とコンデンサだけの簡単な回路ですが、応用範囲が広く、「いたるところで」活躍しており、その使用目的によって、様々な呼び方がされています。周波数帯域制限に着目する場合には、ローパスフィルタ(LPF)、あるいは、ハイパスフィルタ(HPF)です。信号の直流成分を扱う場合には、平滑回路、平均値回路、リップルフィルタですし、また、交流成分を取り出す目的では、直流阻止、DCカットなどと呼ばれます。他にも、積分回路、遅延回路などと呼ばれるような使われ方もあります。
今回は、平滑回路(平均値回路、リップルフィルタ)として使われる、RC回路を取り上げます。
まず、矩形波に対する応答を調べてみましょう。シミュレーションファイル「RCフィルタ矩形波応答.asc」を参照してください。入力信号は、振幅0V-5V、周期100μS(周波数10KHz)、デューティー比50%の矩形波で、RC回路の時定数は、1μS、10μS、100μS、1mS、10mSです。入力矩形波の周期に対して、時定数を1/100~100倍の範囲で変えて、出力応答の様子を調べます。結果は、以下の通りです。
時定数1μS(周期の1/100)、ほとんど入力信号と変わらず、平均値は得られない。
時定数10μS(周期の1/10)、かなり「なまった」波形となるが、平均値は得られない。
時定数100μS(周期と同じ)、平均値に落ち着くが、リップルが大きすぎる(1.22Vpp)。
時定数1mS(周期の10倍)、6mSほどで平均値に落ち着く、リップル126mVpp(5Vに対し2.52%)。
時定数10mS(周期の100倍)、60mSほどで平均値に落ち着く、リップル13mVpp(5Vに対し0.26%)。
容易に予想されることですが、応答時間(出力が落ち着くまでの時間)と出力リップルの大きさとの間に、相反関係があります。要求される特性にもよりますが、大ざっぱに言えば、周期の10倍程度の時定数を目安にすればよいのではないか、と思われます。
RC平滑回路の特性改善を目指して、多段RC回路の特性を調べてみましょう。シミュレーションファイル「多段RC平滑回路.asc」を参照してください。収められている多段RC回路は、同じ定数のRCを縦続しただけですが、明らかに特性の改善が見られます。たとえば、時定数1mS(周期の10倍)1段の回路を基準として比較してみると、時定数100μS(周期と同じ)4段の回路は、応答時間は同じですが、リップルは3.2mVppとなっており、大幅に改善(1/40)されています。また、時定数100μS(周期と同じ)2段の回路は、リップルは同等ですが、応答時間は2mS以下(3倍高速)になっています。この結果を見ると、RC回路の時定数と段数の組み合わせを最適化すれば、かなりの範囲で、望みの特性を実現できそうです。何と言っても、RCは「安い」ですから、気軽に使えます。
おまけとして、シミュレーションファイル「PWM復調デモ.asc」を用意しました。最近では、PWM信号(パルス幅変調信号)は、よく使われています。簡易なアナログ方式の復調回路としてRC回路が使えることを(初心者向けに)示しています。
今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、リニアテクノロジーのサイトよりLTspiceIVをダウンロードしてご利用下さい。