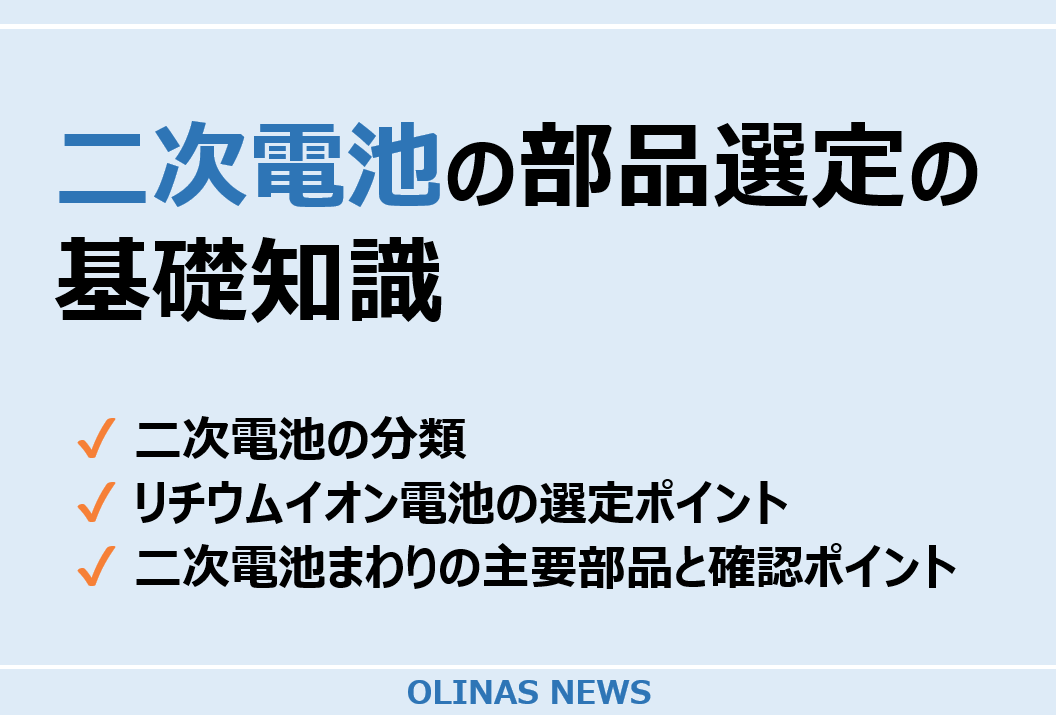単純な抵抗分圧回路の出力電圧を電卓で計算したところ、変な答えになった・・・、こんな経験はどなたにでもあるのではないでしょうか。電卓のキーを間違えているだけのことなのですが、積極的に(?)間違えて、1KΩと-2KΩの分圧回路を計算してみます。Vout=Vin×-2/(1-2)で、2倍の出力電圧になってしまいます。マイナスの抵抗値を指定するだけで、増幅できますので、設計が楽になり・・・ません。
現実の部品としての「負性抵抗器」は存在しませんが、ある条件で負性抵抗をもつ回路はいくつもあります。共振型の発振回路、ないしは、アンプが特定の周波数で発振気味の時など、等価的に負の抵抗として振る舞うと解釈できます。少し乱暴な見方かもしれませんが、能動素子(増幅回路)と負性抵抗は、本質的に等価と考えられそうです。正の抵抗は電力を消費しますが、負の抵抗は電力を供給しますので、この考え方はそれほど「とんでもない解釈」ではないかもしれません。
負性抵抗素子といえば、エサキダイオード(トンネルダイオード)、ラムダダイオードがありますが、使われているのを見たことはありません。かなり昔のことですが、「エサキダイオードは、高速すぎる上に、2端子素子であるため、使うのが難しい」と何かの本で読んだ記憶があります。動作原理がトンネル効果に基づいているため、「とてつもなく」高速なのでしょう。なんといってもノーベル賞ですから・・・。
ラムダダイオードは、NチャネルJFETとPチャネルJFETを組み合わせて2端子素子としているもので、印加電圧を大きくしていくと、初めは電流が増大していきますが、ある電圧を越えると、電流が減少する領域が現れます。十分大きな電圧では、全く電流が流れなくなります。同じような特性を持った回路は、トランジスタ2石以上を使って作れそうです。JFETでなくても、MOSFETでも、バイポーラでも、それらの組み合わせでも(たぶん)可能と思いますが、具体的な回路を発見(?)したわけではありません。興味のある方は挑戦してみてください。
付属のシミュレーション回路について、簡単な解説をしておきます。
1.冒頭で計算した負性抵抗による分圧回路を示してありますが、もちろん意味はありません。シミュレーションでマイナスの抵抗値を受け付けることに驚嘆したため、載せておきました。
2.ラムダダイオード回路は、2つの書き方で示してあります。このように書き換えると、フリップフロップ回路、マルチバイブレータ回路と似ていることに気付くのではないでしょうか。2つのトランジスタで正帰還接続になっていることがわかります。電圧電流特性を鑑賞してください。
3.ラムダダイオードでLC発振ができることを示してありますが、あくまでもデモンストレーションです。波形を見ていただけるとわかりますが、とくに優れているとも思えません。抵抗を追加して特性をチューニングすることは可能でしょうが、1個作りならともかく、あえて採用する回路ではなさそうです。ラムダダイオードの特性で面白いのは、負性抵抗領域よりも遮断領域ではないかと思います。過電圧保護などに使えるのでは、と考えてしまいますが、これまた、「ラムダダイオードでなければ」というほどでもないようです。
4.オペアンプによる回路は、電子負荷回路のつもりで「配線をまちがえた」回路です。これも負性抵抗特性になっています。当然、これも無用の長物かもしれませんが、なにかのヒントになる可能性は否定できません。
電子回路の面白いところは、少しの変更(誤配線)でまったく異なる特性を持つことがあることです。実機での場合には、煙が出たり、最悪で爆発などといった危険がありますが、シミュレーションでは、パソコンが壊れる心配はありませんので、安心してアイデアを試すことが出来ます。よい時代になったものです。おおいに活用して、新しい回路を試してみることをお勧めします。
今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、リニアテクノロジーのサイトよりLTspiceIVをダウンロードしてご利用下さい。