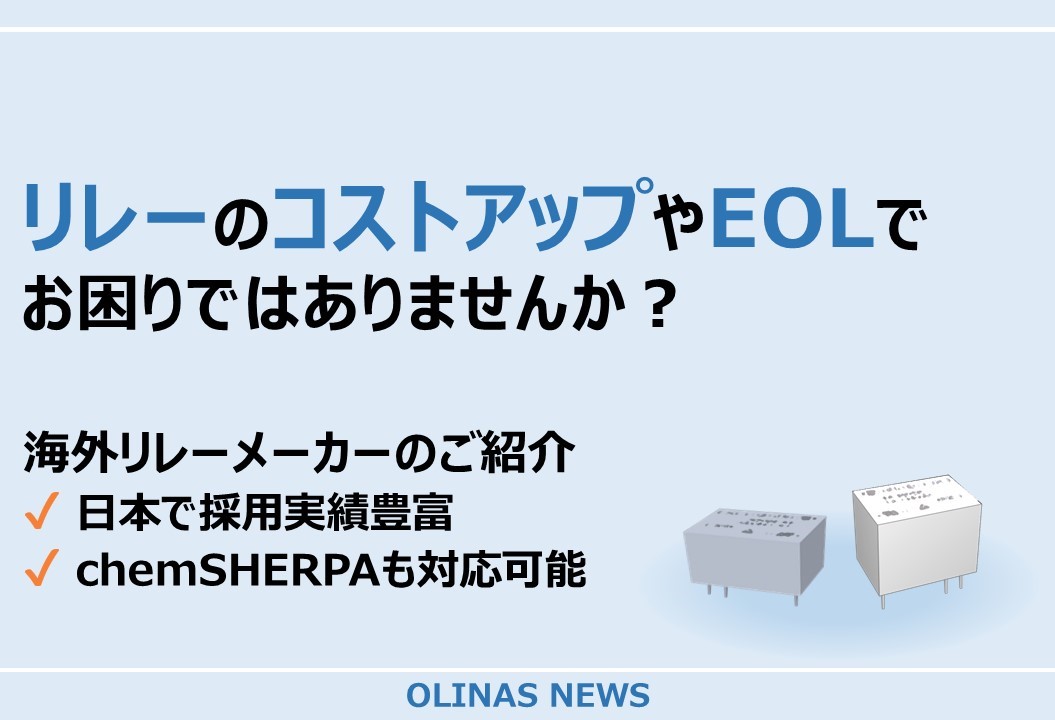前回の最後に紹介した「定電流回路_オペアンプ_2」は、バイラテラル回路と呼ばれる、電流出力アンプ(トランスコンダクタンスアンプ、VI変換回路)です。
私が初めてこの回路を使った時は、バイラテラル回路の存在を知らなかったため、(必要に迫られて)独自に「発見」した回路でした。そのため、この回路の特性をかなり詳しく考察しました。なにせ、見たことも聞いたこともない回路でしたので、「不安」だらけでしたから・・・。
その後、某半導体メーカーのデータブック(昔は分厚い本でした)に、アプリケーション回路例として、記載されているのを見つけましたが、その時は、安心すると同時に、「温故知新」を思い知らされました。
付属の「電流出力アンプの導出」PDFファイルを参照してください。電流出力アンプ回路を「発見」した思考過程を整理して、論理的にまとめたものです。白状しておきますが、当時は、何度も試行錯誤を繰り返し、いくつもの「ボツ」になった回路を「考案」したものです。理路整然と考察を進めて「発見」したわけではありません。
以下、ファイルの内容について解説していきます。
電流出力アンプを「編み出す」きっかけとなったのは、「負荷はシングルエンド接続(片側はグランド)」、「両極性の電流出力」という二つの要件でした。
負荷に流れる出力電流を制御するためには、電流検出抵抗が必須でしょうし、普通に使える出力アンプは、電圧出力アンプですから、出力部分の構成は、図1のようになります。
ファイル内に示したように、アンプ出力電圧の関係式(1)と、目標とする特性(出力電流は制御電圧に比例)とを比較すると、関係式(2)を満たすようにすればよいことが分かります。
関係式(2)を満たす構成概念を図示したものが、図2です。
図3は、図2の構成概念を具体化した回路です。電圧加算器には、一般的な反転加算アンプを使い、後段に反転アンプを入れて極性を合わせています。電流制御電圧は、増幅度=Aの非反転アンプで増幅し、負荷電圧はバッファアンプを介して、それぞれ加算回路に入力しています。このバッファアンプは、負荷電圧の出力インピーダンス(負荷と電流検出抵抗の並列合成インピーダンスで、一般的には不定と考えるべきもの)による影響をなくして、正しく加算するために必要です。
図3の回路では、反転加算アンプ+反転アンプで極性を合わせて非反転加算としている部分が「無駄」に見えます。ご存じのことと思いますが、オペアンプ一つで非反転加算アンプが構成可能です。
そこで、電圧加算器を非反転加算アンプとした回路が図4です。この回路はオペアンプによる差動アンプの形ですから、抵抗の定数を変えることで、負荷電圧の加算係数を1のままで、電流制御電圧入力にゲインを持たせることができます。つまり、増幅度=Aの差動アンプとして、Vref入力に負荷電圧を与えればよいわけです。
このようにして、電流制御電圧入力側にあった、増幅度=Aの非反転アンプを省略した回路が図5です。「めでたく」電流出力アンプ(バイラテラル回路)が得られました。
この回路構成は、差動アンプそのものですから、ゲインを自由に設定することはもちろん、入力を反転入力とすることも、差動入力とすることもできます。さらに、入力を拡張することで、オフセットなどの追加の入力端を設けることもできますので、非常に使い勝手が良い回路となっています。入力の拡張方法については、次回以降に、具体的に示す予定です。
次回は、この電流出力アンプ回路の入出力特性を詳しく解説します。