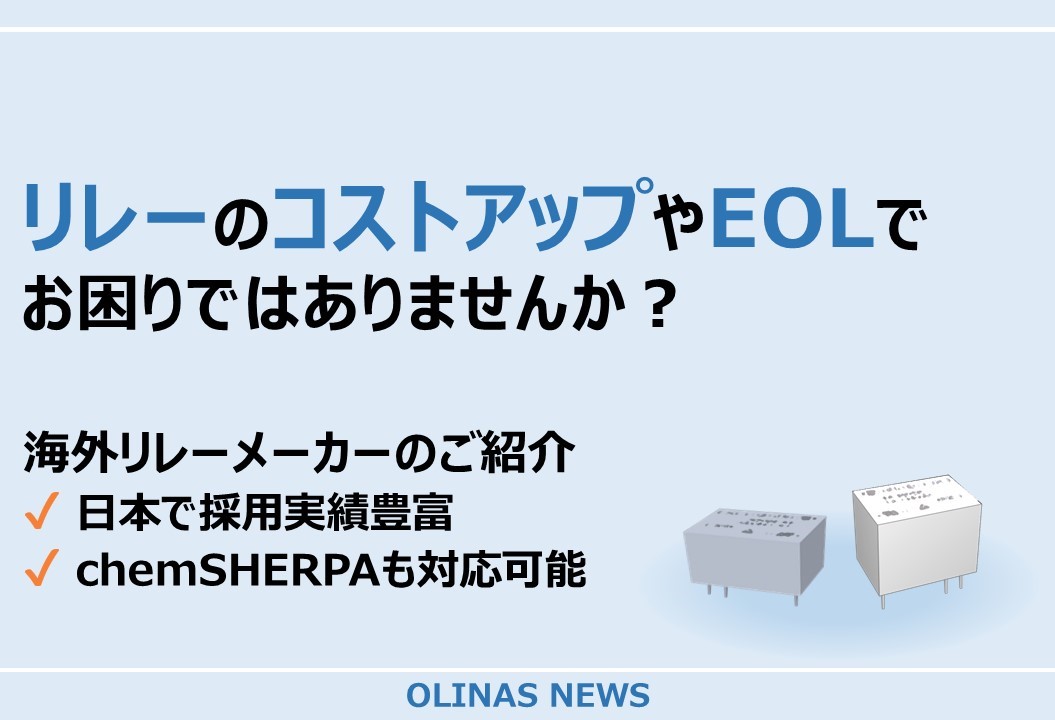前回、オペアンプで差動アンプを構成し、Vref入力端に負荷電圧を入力すれば、電流出力アンプが得られることを解説しました。出力電流Ioutと入力電圧Vinの関係は、差動アンプのゲインをA、電流検出抵抗をRsとすると、
Iout = A × Vin / Rs
となります。あるいは、VI変換コンダクタンスgm = A/Rs と表すこともできます。
この関係式が「何と無くピンとこない」ならば、負荷抵抗をショートした回路で考えてみてください。こうすると、Vref入力をグランドに接続した普通の差動アンプの出力に、電流検出抵抗Rsを負荷抵抗として接続している回路となっていますから、容易に出力電流を計算できます。
ここで、この電流出力アンプの動作原理をやや「文学的表現(?)」で解説を試みます。まず、この回路のVref入力への負荷電圧入力を無視し、出力抵抗Rsの電圧出力アンプと見做します。差動アンプの出力抵抗はゼロと考えてよいでしょう。その出力に電流検出抵抗Rsが直列に接続されていますから、負荷から見た出力抵抗はRsです。一般に出力から負帰還を掛けると出力抵抗は小さくなりますが、この回路では、正帰還となっていますので、出力抵抗は大きくなるのではないか、と推察します。出力抵抗が極めて大きくなり、無限大となれば電流源となる、と考えられます。正帰還のループゲインが1ならば、その条件が成り立つような気がします・・・このような考察が、有益かどうかの判定は、みなさんにお任せします。
シミュレーション回路「電流出力アンプ_gm設定.asc」には、簡単な例を示してあります。入力1Vで10mAを出力する回路と、出力を半分の5mAにするために、差動アンプのゲインを1/2にした回路、および、電流検出抵抗を2倍にした回路を収めています。定数を変えたり、入力を「お好みの」信号としたり、いろいろ遊んでみてください。
予習テーマ
余裕と興味のある方は、正帰還のループゲインを変えて、出力抵抗がどのようになるか調べてください。計算で求めても結構ですが、計算結果の数値だけでは、回路動作の感覚は「つかみにくい」と思います。これは、次回以降に解説する予定のテーマです。
入力の拡張
電流出力アンプは、差動アンプそのものですから、当然のことながら、その入力拡張は、差動アンプの入力拡張と全く同じ方法で実現できます。シミュレーション回路「入力拡張差動アンプ.asc」に簡単な例を示してあります。
入力を追加するには、「必ず」反転入力と非反転入力をペアで、かつ、同じゲイン(同じ入力抵抗値)とすることが肝要です。反転入力、または、非反転入力だけを使う場合でも、ペアで追加し、使わない方は、グランドに接続するようにしなければなりません。いくつかの入力抵抗が並列にグランドに接続されている場合に、それらの並列合成値の1本の抵抗とすることは問題ありません。
原理的には、入力ペアをいくらでも増やすことができますし、入力ペアごとに異なったゲインを持たせることもできますが、ループゲインが「食われ」ますので、特性は悪化します。このあたりの事情は、反転加算アンプの場合と全く同じです。
電流出力アンプを実際に製作する場合、抵抗値には誤差がありますから、正帰還のループゲインは正確に1とはなりません。このため、出力の定電流特性が損なわれる(出力抵抗が無限大ではなくなる)のですが、これがどの程度になるか、次回、検討してみたいと思います。
今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、リニアテクノロジーのサイトよりLTspiceIVをダウンロードしてご利用下さい。