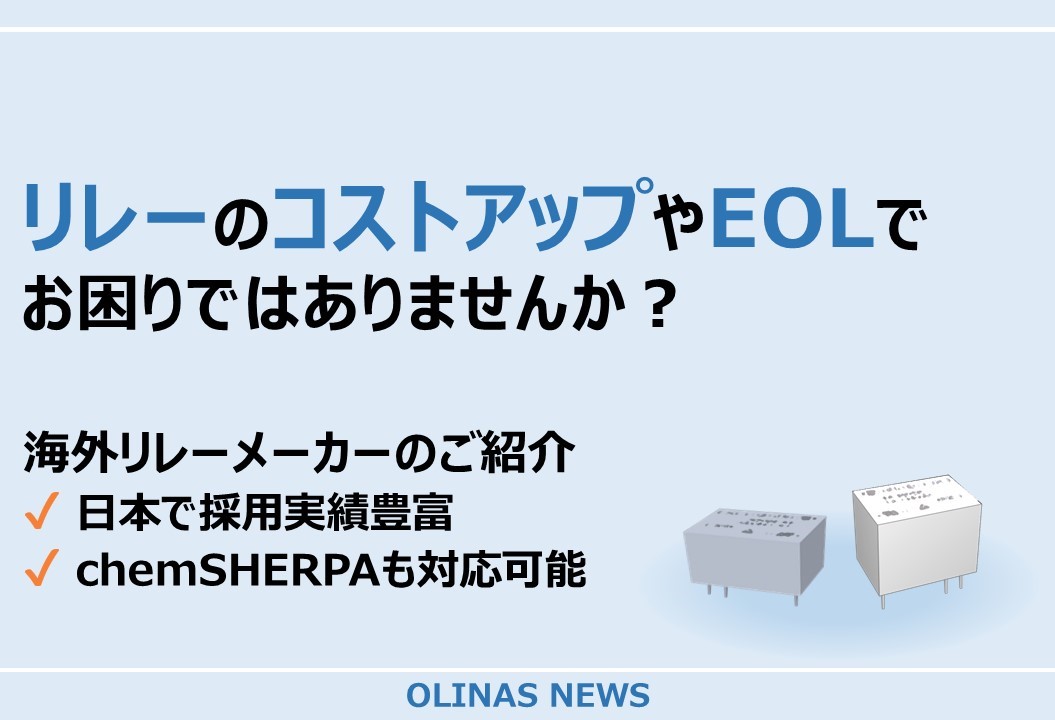①電圧信号における分解能とは
種々の量を電気信号に変換して測定することは、電子技術の重要な応用の一つです。測定結果は、適切な表示をする、制御ループに入力する、など、各機器・装置ごとに異なりますが、測定そのものの質(測定性能)の良し悪しが、各機器・装置の性能に直結します。
測定性能には、いくつかの項目がありますが、ここでは、分解能について考えてみます。「分解能とは何か」は、説明するまでもないと思いますが、不安のある方は、広辞苑などで調べてください。
測定値は、最終的に(適切なレベルの)電圧信号に変換することが一般的です。これは、アナログ信号のまま使う、ADコンバータに入力する、など、後段の処理に都合がよいからです。
得られた電圧信号での分解能とは、識別可能な最小電圧差、または、検出可能な最小電圧値ですが、結論を以下に示します。
分解能≧ノイズ電圧(Vpp)
分解能は、ノイズレベルで決まってしまいます。例えば、高分解能のADコンバータを使っても、システムとしての分解能を改善できるわけではありません。
シミュレーション
付属のシミュレーションファイルには、簡素化したデモンストレーションとして、ノイズが重畳した信号をコンパレータに入力して処理する回路を収めてあります。
シミュレーションファイル「分解能とノイズ_デモ_1.asc」は、基準電圧が0Vと1Vの、2つのコンパレータに単調に増大する電圧信号を入力しています。基準電圧の差1VをADコンバータの最小電圧差(1LSB)と見做してください。ノイズの代用として0.5Vpp、1Vpp、2Vppの正弦波を重畳しています。
ノイズが大きい場合、コンパレータの出力が安定せず、ADコンバータであれば、最下位ビットがバラついて、分解能が十分得られない状態です
シミュレーションファイル「分解能とノイズ_デモ_2.asc」は、1Vの矩形波を入力しています。コンパレータの基準電圧は、0.5Vです。ノイズの代用として0.98Vpp、1.02Vpp、2Vppの正弦波を重畳しています。
ノイズが1Vpp未満の場合は、コンパレータ出力に信号が検出されていますが、ノイズが1Vppより大きくなると、コンパレータの出力は不定状態となり、信号を検出できていません。
2Vppのノイズが重畳した信号を見てください。人間の目には、信号があることが見て取れるのです。なぜでしょうか。これは、全体を見ている、すなわち、長時間に渡る多数の情報を脳内で処理しているためです。一方、コンパレータは、瞬間、瞬間の電圧値のみで判定しています。
この「現象、錯覚」は、肝に銘じておくべきです。オシロスコープでノイズが大きい(S/N比が十分でない)信号を見て、「これならイケル」と思っていても、出力が安定しない(分解能が足りない)結果となる恐れがあるからです。
②今回のまとめ
原理的には、分解能=ノイズレベルでよいのですが、実用設計の場合、安定動作などを考えると、「余裕」を持たせたくなります。私の個人的な感覚では、分解能=ノイズレベルの2~3倍くらいを目安としていますが、妥当な「余裕」は、やはり、個別に判断すべきです。
次回、いくつかの具体例について、分解能を見積もってみたいと思います。
今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、リニアテクノロジーのサイトよりLTspiceIVをダウンロードしてご利用下さい。