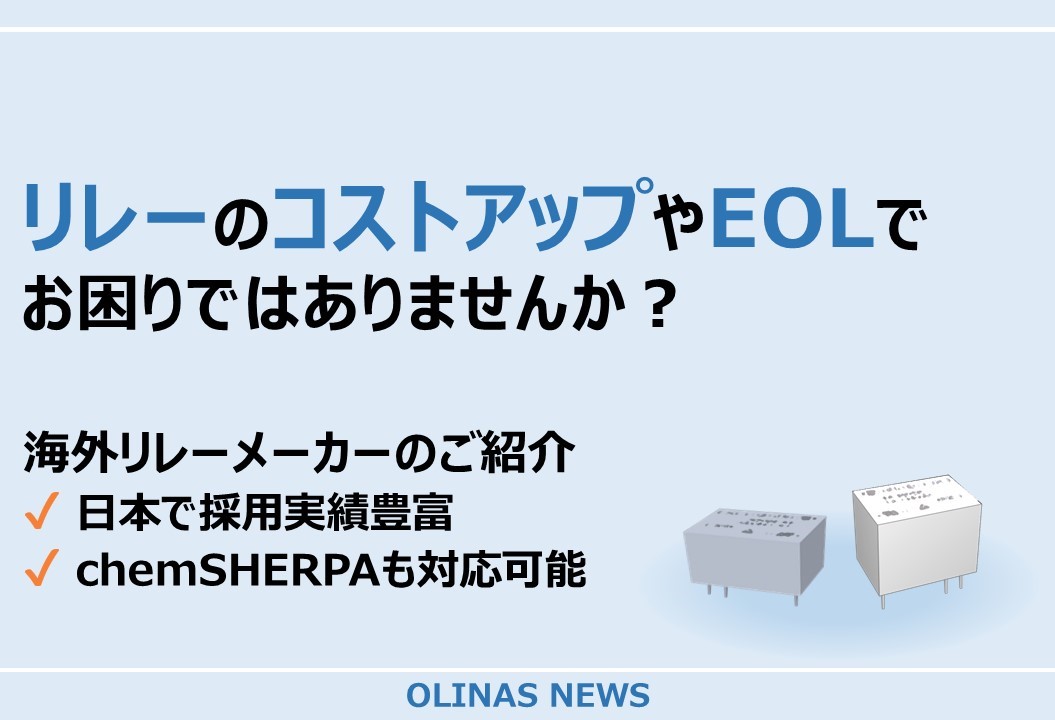電気・電子回路における非線形回路 -アナログ乗算器IC(1)-
①はじめに
アナログ乗算器というICがあります。この種のIC内部では、どのような動作原理で乗算をしているのか、調べてみました。その結果、「トランスコンダクタンス」「ギルバートセル」「トランスリニア」などの用語、および、多くの計算式を発見しました。
今回は、AD社の資料(チュートリアルMT-079)に記載されている簡略化された等価回路をもとにシミュレーション回路を作成して、その動作を確認してみたいと思います。
②アナログ乗算器のシミュレーション
シミュレーション
シミュレーションファイル「アナログ乗算器IC回路.asc」を参照してください。
上記資料の回路(AD534)を参考とした回路です。動作の本質に関係がなさそうな部分は、理想要素で置き換えてあります。また、抵抗値、入力電圧レベルなどは、資料に記載されていないため、おおよその値を設定してみました。Vx入力にはDCを想定して-0.1V~+0.1V、Vy入力には振幅0.1Vの正弦波を設定してあり、きれいな4象限の乗算出力が得られています。ゲイン(スケールファクタ)は、0.1V?0.1Vのとき、約0.3Vの出力となっています。
次に、少し変形、変化させた回路で各部の電圧・電流を確認してみます。
シミュレーション
シミュレーションファイル「アナログ乗算器IC回路_変形_1.asc」を参照してください。
出力部分で2つの差動電流出力を加算していますが、それぞれの差動出力はどうなっているか、確認できる回路に変形しました。
Vout_1、Vout_2をみると、VxとVyの乗算出力にVx入力成分が逆極性で重なっています。これをみると、2つの差動電流出力を加算することによって、Vx入力成分を打ち消していることが理解できます。
シミュレーション
シミュレーションファイル「アナログ乗算器IC回路_変形_2.asc」を参照してください。
入力部の差動トランジスタペアのエミッタ間の抵抗値を変えてみた回路です。Vx入力部のエミッタ抵抗を1KΩから500Ωに変更した回路とVy入力部のエミッタ抵抗を1KΩから500Ωに変更した回路を収めてあります。
Vout_1、Vout_2ともに、出力レベルが2倍弱に大きくなっていますが、波形には有意な差は無いようですから、ゲインには関係するものの、乗算動作の本質には影響は無い(あるいは、影響は少ない)ようです。
Vx入力の差動トランジスタのコレクタ負荷はダイオード(接続のトランジスタ)となっています。コレクタ電流変化に対して逆対数変換しますから、この部分は、レベルシフトではないか、と予想しました。
シミュレーション
シミュレーションファイル「アナログ乗算器IC回路_変形_3.asc」を参照してください。
Vx入力部の差動出力をみると、レベルは小さいですが、Vx入力と相似となっています。確認しやすくするために、Vx_dif_Out_x10は、10倍に拡大しています。
Vx入力差動回路部分(レベルシフト)を省略した回路を収めてありますので、乗算出力を比較してください。多少のゲインの違いはありますが、動作としては等価であると結論できます。
今回のまとめ
次回、引き続きアナログ乗算器ICの回路取り上げる予定です。
今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、アナログ・デバイセズのサイトよりLTspiceをダウンロードしてご利用下さい。
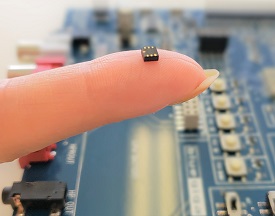
国内初!!超小型、6V入力DC/DCコンバータ新登場!!
業界最小サイズ!:独自開発のパッケージングで実装面積は3mm×3mm、厚さ1.4mm
抜群の変換効率!:最大90%以上
詳細は ここ をクリック
ご興味、ご関心のある方は「お問い合わせ」をクリックの上、ご連絡下さい。